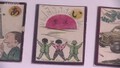■【戦後80年】子どもたちに憲法の意義を伝える「憲法歌留多」 能代第二中学校で大会も 受け継がれる精神(秋田県)
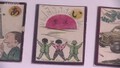
5月3日は憲法記念日です。
現在の憲法は、いまから78年前、1947年の5月3日に制定されました。
主権在民・基本的人権の尊重、そして戦争放棄を柱とした憲法は、戦後の平和と繁栄の礎になっています。
戦後80年、「いまを戦前にさせない」。
2日は、当時の子どもたちに新たな憲法を理解してもらうため、能代市の中学校で作られたという「憲法歌留多」についてお伝えします。
細川愛さん
「憲法というもの、戦後の80年を実際にはずっと支えてきた憲法というものも、戦後80年にとって非常に大事なことなんじゃないかなというふうに考えています」
先月、秋田市で開かれた、郷土史の講演会。
男鹿市などで社会科の教員を務めてきた細川愛さんが、戦後80年を語る題材として取り上げたのが、かつて能代市の中学校で使われていたという「憲法歌留多」です。
細川さん
「能代二中で作られたというところ、ここのところによく表れています。この黒板に書かれているのが、能代第二中学校一年B組級長選挙。『級長選挙には一人もれなく投票してください』と参政権のことを表したかるたなんですけれども、男女一緒になって、しかも能代二中という、本当に地元の子どもたちのことを考えて作られたものだなというふうに思います」
現在の日本国憲法が制定された1947年、昭和22年に創立された、能代第二中学校。
校舎の一角に設けられた資料室に、憲法歌留多の実物が大切に保管されています。
「いまこそ生かせ 民定憲法」
「日本の象徴 われらの天皇」
「類例稀なる 戦争放棄」
ユーモラスのある絵札は、能代に疎開していたというプロの漫画家が手掛けたとされていて、当時、校内で歌留多大会が盛大に行われたという記録も残っています。
新たな憲法をどうやって子どもたちに理解してもらうのか。
当時の教員は、条文をしっかり読み込んで、憲法の精神を表現していました。
しかし、間もなくして「憲法歌留多」は時代の流れに埋もれてしまいます。
細川さんは、その背景に、能代を襲った大きな災害が関係していると考えています。
細川さん
「(昭和の能代)大火でだいぶ焼けてしまったという話もあって、それでまず数が少なくなっていたということが一つ大きいと思いますね。あちこちで使っていれば、うちにもこんなのがあったよってことになったと思うんですけど」
人々の記憶から忘れ去られた「憲法歌留多」。
ただ、憲法を尊ぶ精神は、校歌にも刻まれていて、いまも能代二中の生徒たちに受け継がれています。
校歌の歌詞
「大いなる平和をにないゆくわれら国ひらく憲法のこころ身につけて」
細川さん
「戦争から80年経ったけれども、いろんな人が戦後の思いを持ちながら、ここまで来て、それぞれの家の歴史をたどっていったりすると、やっぱり何らかの形で、みんな戦争と関わってきている」
「戦後80年というのは、決して最近生まれた人にとっても遠いものではなくて、みんなどこかで関わってきていると。その80年を、憲法というものが支えてきているのだなというふうに感じています」
??????????
憲法歌留多を調べている元教員の細川さんは「現在の学校現場は多忙で、歌留多そのものを授業で生かすことは難しいが、子どもたちに伝えていく取り組みや、働きかけを期待している」と語っています。
また、細川さんは「県内のほかの地域でも憲法歌留多があったかもしれない」とも話していました。
秋田放送では、今後も「いまを戦前にさせない」をテーマに、様々な特集をお伝えしていきます。
戦争に関する日記や写真、映像などの資料をお持ちの方は、こちらの二次元コードから情報をお寄せください。
(05/02 17:51 秋田放送)
・TOP
Copyright(C)NNN(Nippon News Network)